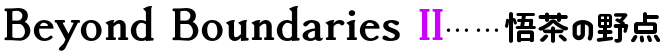これは2012年2月17日の投稿(つまり旧ブログ開始2周年!)で、やはり作曲家、玉木宏樹氏(故人)の書籍を紹介した記事でした。
このところずっとdrone/ambient系の音楽ばかり聞いています。……といいますか、それ以外の音楽を聞きたくありません。なんでだろう……。
そのことと遠からず関係があるのは恐らく528Hz LOVE Tone(及びソルフェジオ)に加え、純正律。
純正律のエバンジェリスト、玉木宏樹さんはヴァイオリニスト/作曲家ですが、文筆家としても優れた作品を著されています。その中の一冊「純正律は世界を救う」(2002年)からの抜粋です。
◉ジャズとロックにおける純正律的矛盾
平均律で作曲することに精魂傾けたドビュッシーの和声理論を基に展開しているのが、ピアノやギターという平均律(ギターはそうともいえないが)を中心にしたアンサンブル、モダン・ジャズの世界である。このジャズの世界と後のロックの世界、これは純正律的に考察するととても興味深い世界である。
もちろん、私はクラシックの勉強をしていたから、意識してジャズを聴きだしたのは高校の後半くらいで、その頃「ダンモ」と呼ばれていたモダン・ジャズが全盛になる直前の頃だったと思う。だから、それ以前のスウィング系やフルバンド系は後から聴いている。
私の頃は、マイルス・デビス、チャーリー ・パーカー、ソニー・ロリンズ、コルトレーンとか、今で言えば懐かしい名前が大活躍していた。最近、ある音楽雑誌の若い編集者達といろんな話をした時、「私は耳コピーには大変自信を持っていたので、エリック・ドルフィーはコピーできたけど、オーネット・コールマンは駄目だった」と言ったら、本当に二人の違いが分っていたらしく、しばらくのあいだ涙を溜めながら笑い転げていた。
今、ジャズと言えば、フュージョンやスムース・ジャズが多い。このジャンルはたとえ平均律であれ、音楽的には非常に行儀よく、その面では安心して聴いていられるが、その頃のダンモの音程は悪いなんでものじゃなく、音程の悪さを競っているようなところがあった。
芸大に入って東京のジャズ喫茶に行った時、その当時の意識の高そうなジャズファンの学生達は一様に、読んでもいないサルトルを片手に実に深刻な顔をしてジャズで瞑想していた。が、私にとってどうにも理解しがたく我慢のならないのは、トランペットやサックスが吹くリフ・メロ(クラシックで言えば「主題」と「変奏」の主題にあたるところ)の音程を、もうメチャクチャといっていいほど外しまくっていることだった。例えば、オクターヴ・ユニゾンのはずが、なぜか二人とも絶対にハモるまいと意地を張っているかのように音程がゆがんでいた。その最も典型なのが、前記のオーネット・コールマンで、これはもう、私には音痴以外の何ものでもなかった。ジャズに詳しそうな人間になんであんなに音程が悪いのかと訊いたところ、したり顔で次のように答えた。
「あれは、リズムのノリに合わせた結果なんだよ。なんてったって、ズージャはノリが命だからな。クラシックなんて、音程はいいけど全くノリがなっちゃいない」
私は分ったような振りをしながらも全く賛成はできなかった。エリック・ドルフィーやコルトレーンのように、細かい所では無茶苦茶に音程のいい人もいる反面、ヘタウマに見せようとしているマイルス・デビスも好きになれなかった。だから、平均律の権化であるピアニストのビル・エパンスやオスカー・ピータースン、MJQなんかの方がよほど安心して聴けたのだった。
では、リフ・メロを吹くペット、ホーン、サックスは、なぜあんなに音程が悪かったのだろう(ケイレン的な無茶苦茶アドリブをやる為の予防線を張ったようなコールマンを除いての話だが)。
今、私が懸命に純正律の歴史を研究している見地から、なんとなく想像できることがある。
もちろん理論で解明したわけではないのだが、当時の音楽の流れをたどってみると、おぼろげに分ってくる気がする。
私はジャズにはそんなに詳しくはないので、間違いがあれば指摘していただきたいが、モダン・ジャズというのは、それまでのビッグ・バンド系ジャズが、単なるクラブのダンス系バックであり続けることに頭にきた何人かによる、各自の個性がはっきりと分る4~5人の室内楽を始めたのがルーツではないかと思う。
そして、その(グレン・ミラーを筆頭とした) ビッグ・バンド系は、アレンジもアンサンブルもクラシックのどんなオーケストラでも真似のできないほど水準が高く、非常に気持ちのよいハーモニーとアクロバット的なリズム感で大衆を魅了していた。弦はほとんど入っておらず、ブラス主体のバンド系は、絶対に音程を外せない。一人でも間違ったり外したりした瞬間に快いハーモニーの世界は瓦解する。今でもブラスバンド出身の人なら分るだろうけど、自分の周りが純正律的にハモっていないと非常に不愉快で、身体に悪い感じを抱くと思う。だから、ビッグ・バンド系のプラスは非常にハモりのいい純正律で吹いていたはずである。今でも5サックスのコード・ブロックによる動きは、音程がよいほど快感が増す。
まあ、あえて飛躍すると、そんな快いバンド全盛時代も、所詮ダンスのバックでしかなかったことに飽き足らず音楽演奏だけの主張を始めたのが室内楽のダンモだとしたら、がんじがらめの音程の束縛から離れ、どんな音程で吹いても自分の勝手とばかり、ハモらないことを一種の自己主張と勘違いした面があるのではないだろうか。
それからもう一つ、重要なファクターがあると思われる。それは、それまでのバンド系では単なる脇役でしかなかったピアノとギターが、アンサンブルの中心となったことである。
平均律のピアノやギターは原則的には何調でも同じように狂いのない(実は全てを平均的に狂わせてある)、絶対的な音程で演奏する。それに対抗した音程感なのだとしたら、「反純正律、反平均律」でなんの拠り所もない自己主張の音程になるしかないので、彼らはあんなに外れた音を吹いていたのだろう。
ところで、モダン・ジャズはプレスリーや初期ビートルズのようなロックンロールには見向きもしなかったが、音楽的に目覚しい成果を発揮しだした『アビーロード』以後のビートルズに影響を受けたロックバンドには、脅威を覚え始めたようだ。そして、何事にも冒険心の強かったマイルス・デビスが、あれほどパカにして避けまくっていたエイト・ビートを、しかもエレキトランペットで始めたことによって、ジャズは一気にフュージョンへと進む。しかし、このエレキ化が、暖昧な音程を駆逐した。当然である。
全く音程が悪くてハモらない不協和音(それも調性がちゃんとありながら) をアンプリファイアされた大音量で流されたら、誰もが逃げ出してしまう。だからジャズはフュージョンになって以来、急に音程が良くなった。と言っても、所詮、平均律の上のことだけど。
一方、ロック・バンドの場合、ピアノやシンセ等のキーボードが入るのは大分後のことで、初期は、ただデカい音を出すだけのビートルズのような暴走族の騒音に似たエレキギターを中心に成長した。初期のビートルズ(ドイツのハンブルク時代) があまりの騒音の激しきのために逮捕された話は有名だが、彼らがなぜ大音量を必要としたのかは、これから述べるロック・バンドにおける純正律的矛盾と大いに関係があると私は考えている。
もともとギターの調弦では「ソ」と「シ」という長三度を純正律的にハモらせると、全体が崩壊するという自己矛盾を抱えている。だから最近のギタリストは平均律のチューニングメーターに頼っているようだ。
今の若いミュージシャンの大半はエレキギターをやった経験があるし、ミュージシャンを目指してキュイーン、キュイーンと騒音を撒き散らしていた経験のある若者も大変多いので、私が以下の話をするとみんなが納得する部分がある。
私がいくら純正律の話をしても、ギターしかやってこなかった人は、「自分はギターなんだから、所詮関係ない」と言って、純正律の素晴らしいCDをかけても、いくら細かく説明してもなかなか自分のこととは感じてくれない。そんな場合、私はギター弾きの人たちに言う。「君たち、エレキ・ギターの下の方で『ドミソ』を鳴らしたことがあるか」と。すると、ほとんど全員、「いや、三度は抜きます」と言う。「どうして」と訊くと、「だって『ドミソ』は汚いから、『ミ』は抜いて、五度だけならよくやります」と答える。これがロック・ギターの純正律的矛盾である。プリセットのシンセには、ギターの五度というのもあるくらいだ。
クラシック・ギターやハープ、ピアノ等、音が減衰する楽器についての、瞬間的に汚い「ドミソ」はほとんど問題にはなり得ないが、ギターは記譜より一オクターヴ低く、また、もともと純正律でも低い方の「ドミソ」は敬遠するようにいわれるほどハモりにくい。そこへ大音量での濁った「ドミソ」を鳴らすことは、ギター弾きにとっても相当堪えるはず。
その話をすると、みんなは「なるほど」と納得、平均律の「ドミソ」の汚さを初めて実感し、「そういえば、キーボードのヤツらからは、なぜ三度を抜くのかと言われていつもケンカになった」という話さえするようになる。エレキ・ピアノやシンセは、もともとその汚い三度の響きに対して耳を船酔い状態にするコーラスやフランジャー等のエフェクターを多用しているから、自らの音の汚きには気付いていない。
きて、ロック・バンドでツイン・ギターの場合、もっと強烈な矛盾がはっきりする。それは、リード・ギターがハーモニックス奏法を多用した時だ。一弦上でのハーモニックスは、完全な倍音奏法であり、完全な純正律である。また、ハーモニックスの音は非常に美しく、本人もこのハーモニツクスでなら「ドミソ」も好んでプレイする。とはいえ、隣に居るセカンド・ギターも一緒にハーモニックスをやりだすとへンなので、実音で弾いていると、必ず純正律の「ミ」と平均律的な「ミ」がぶつかり合って悲惨な結果になる。ドラムがなぜ、あのようにうるさくドカドカと叩きまくるのか、それは、この泥沼状態の音のぶつかり合いをマスキングするためのものではないだろうか。
そう考えると、初期のビートルズがうるさかったのも納得できる。彼らは、いつまでたっても満足のいくようなチューニングができなかった。私は「抱きしめたい」だって大変チューニングが悪いと思う。レコードで聴いている限りはそれほどでもないが、ステージともなると、音程の悪さをカバーするため(実は自分を麻痺させるため) にも大音量にならざるを得なかったのだと思う。
そもそも、PAによる大音量とは、大衆を威嚇し手懐けるためにヒットラーによって利用された手法である。そのPAが、ヒットラーの敵対国、イギリスのビートルズによって拡大利用され、大衆をひれ伏せさせた。歴史の皮肉としか言い様がない。
◉もう一度、平均律の効用、そして悪用
前期ロマン派ぐらいまでの音楽は、調性がはっきりしており、それほど複雑で激しい転調はなかったので、平均律を採り入れるファクターがなかったといえる。しかし、ワーグナーの飽くなき転調への欲望は、当時のピアノ調律には向かず、彼はオーケストラを駆使してその欲望を拡大していった。そのせか、ワーグナーにはほとんどピアノ曲が無い。
平均律を深く理解していたドビュッシーは、最初は猛烈なワグネリアンだった。しかし彼は大げさなオーケストラには向かわず、複雑な和声進行をピアノで充分に表現するために、縦割りの響きを犠牲にしても機能的転調が簡単にできる平均律の効用を認め、ついには平均律を美化するためのホールトーンスケールを創造した。
(※悟茶註:ドーレーミーファ#ーソ#ーラ#ード…と全音間隔で並ぶ音階)そのおかげで、世の中は急激に平均律化していった。
その結果、第一章でも書いたが、マリンバ、シロフォン、ヴィヴラフォン、グロツケン、チェレス夕、アコーディオン等々の素晴らしい楽器群が生まれた。また、今もジャズ・プレイヤーに好まれているモダンジャズのコード理論はドビュッシーそのものといってよい。私は平均律のピアノのソロはあまり好きではないが、サウンドとしては、ピアノとヴィヴラフォン、グロッケンのユニゾンは好みだし、ハープとヴィヴラフォンのユニゾンも大好きでアレンジや劇伴作曲の時にはよく使う。そういうサウンドの極め付けは、シャーリングトーンで、盲目のピアニスト、シャーリングが編み出したそのサウンドはブロックコードのピアノとエレキギター、ヴィヴラフォンのユニゾンであり、このサウンドは平均律でなければ実現できない。
一方、悪用ということはないが、ドビュッシー以後、響きの美しきを放棄するのなら、もっと前衛的に、というわけで、シェーンベルク(アルノルト、墺、1874~1951)達の、ドデカフォニスト(12音主義者)が登場し、音楽の重要な要素であるハーモニーを駆逐してしまった。そのためその後、現代音楽の作曲家は長い間メロディを書く必要がなくなり、また分かり易いメロディを書いたりすると大パカにされた。でもこんないびつな音楽が長く続くはずはなく、現代ではポストモダンとしてどんどん純正律音楽が復活してきている。もう一つの平均律の悪用例は、絶対音感至上主義で、狂ったドミソの音当てクイズが跋扈し、子供の音感を根底から駄目にしている。子供というのは、何でも当てっこが好きだから、喜んで絶対音感教育にとりこまれてしまう。
人聞の耳は半音の100分の2の違いでさえ分かるのに、間に合わせの、全ての音の高さを平均律に狂わせてあるピアノのドミソで音当てクイズをやってどうするというのだ。
かくいう私も、中学時代には「天才児」と呼ばれたほど「絶対音感」を持っていたので、ほとんどの音はいっぺんに分かり有頂天だったが、今ではその悪影響からなかなか抜け出せずに、もがき、あえいでいる。これについては前項「純正律の自分史」に説明がある。
絶対音感至上主義になってしまうと、簡単な移調ができなくなる。こういう生活習慣病に陥っている音楽家の多いこと。固定ド唱法と、それにつながる絶対音感教育はやめたほうがいい。音感は、鋭い相対音感の方がよい。
ところで、ジャズピアニストの佐藤允彦氏は、アフリカで平均律を根底からパカにされた体験記を書かれていた。要旨は次のような事だったと思う。
佐藤さん達一行がアフリカへ演奏旅行へ行った時のこと。多分ガーナじゃなかったかと思うが、そこで本番前のリハーサルで、エレキピアノとかシンセ類のキーボード楽器を調整していたところ、現地の人が寄ってきて、「なんでその楽器はそんなに音が狂っているんだ」という。佐藤氏、最初は何を言ってるのか分からなかったが、だんだんと理解できるようになってきた。要するに、楽器の音色がちっともハモっていない、狂って濁った和音だ、と言っているらしい。
佐藤氏は苦りきって、「この楽器は平均律という調律でやっているから、この音の高さになっている」と答えても、「何がどうあっても狂ってる」、「いや、日本でもアメリカでもヨーロッパでも、みんなこの平均律で演奏している」と言っても、現地の人は、「狂ってるものは狂ってる。そんな楽器を弾く方がおかしい」とやられたらしい。
ここで佐藤氏は初めて、世界中では平均律以外のいろんな高さの音程が使われていることに気付いて、カルチャーショックを受けた、という内容の記事である。
マイナーな業界新聞に寄稿していたものを読んで、私もすごくに印象に残った。手元にその記事が見当たらないので、細部に間違いはあるかもしれないが、大筋は間違っていないと思う。
(引用終わり)
10年くらい前だったか、「絶対音感」というノンフィクションがベストセラーになりましたけど、その中で、矢野顕子と渡辺香津美のインタビューが印象に残っています。
矢野さんは多分今も本拠地はニューヨークだと思いますが、彼の地のシャズ系のミュージシャンでも絶対音感がある人は少ないようで、「自分はパーフェクト・ピッチを持っている」というととても羨ましがられるということでした。
一方、ギターなどは多くの人が10代から始めることが多いこともあり、絶対音感を身につけているミュージシャンは少ないと思いますが、渡辺香津美さんも「絶対音感は必要ない。むしろ必要なのは相対音感」と仰ってました。相対音感は訓練次第で身に付くようで、バークリー音楽院などでも、相対音感を徹底的に訓練するプログラムがあるようですネ。
……と、まぁ上記の抜粋の中だけでも興味深い内容がたくさん含まれている名著だと思います。
ところで話が横に逸れますが、
"音楽的に目覚しい成果を発揮しだした『アビーロード』以後のビートルズ"
……という部分でやはり頷いてしまいます。デビュー当時のビートルズはありきたりのロックンロールばかりで何の新味もない凡庸なバンドでしたけど、間もなく急に才能が「埋め込まれた」ように斬新な曲を発表しだして、非常に違和感を感じます。この奇妙な感じからして「タヴィストック人間関係研究所」との関わりがあったことを想像させます。
この部分でもA=440Hzとの繋がりがあるのかな、などと考えつつ『ジョン・レノンを殺した凶気の調律A=440Hz』(原題は""The Book of 528_Prosperity Key of Love""徳間書店2月28日刊)を楽しみに待ってゐるのでござゐます。
以上、旧ブログの人氣エントリより再掲させていただきました。